- 生物の進化と種の保全
- 生物の探求と種の保全
- 種の保全と生物模倣(バイオミミクリー)
- 生物文化多様性(バイオカルチュラル・ダイバーシティ)と種の保全
- 種の保全と自然の権利
- 種の保全と宇宙探査
- 種の保全と芸術
- 種の保全と食文化 ウナギ キヌア スーパーフード
- 種の保全とエコロジカルフットプリント
- 種の保全と子どもの成長
- 生息地の保護と再生 保護区の設定
- 熱帯雨林の再生プロジェクト
- 密漁・密猟・違法取引対策の強化
- 生息域外保全の推進 野生下での存続が極めて難しい場合
- 保全生物学の発展
- 保全政策とガバナンス ワシントン条約や、ラムサール条約、ボン条約
- 持続可能な資源利用の促進 ビクーニャ ワイルドシルク
- 環境教育・自然体験活動の充実
- 企業の参画と生物多様性配慮 CSR(企業の社会的責任)やESG投資
- デジタル技術の活用 密漁密猟防止監視カメラシステム 音響センサー
- 希少野生動物由来の製品のトレーサビリティ(追跡可能性)
- 希少種・絶滅危惧種を守るための包括的アプローチ 社会の総力を結集する保全戦略
- ツーリズムの活用と管理 コスタリカは、エコツーリズム先進国
- 若者の参画促進
- NPO法人 信州ツキノワグマ研究会
- 文化的アプローチの重要性
- アフリカゾウの密猟対策 法的枠組みの強化 ワシントン条約
- 絶滅危惧種を守るための総合的戦略 生物多様性保全の未来を拓く英知
- ユネスコエコパーク(Biosphere Reserve:生物圏保存地域)
- 社会変革の原動力としての種の保全
- 「One Planet Living(一つの地球に暮らすライフスタイル)」
- FSC認証を付けた木材製品やMSC認証の水産物
- 自然との共生の倫理と種の保全
- 土地倫理の提唱者であるアルド・レオポルドは、「生態学的良心(ecological conscience)」という言葉を残しました。
生物の進化と種の保全
絶滅危惧種の保護は、生物の進化の歴史を守る営みでもあります。現在の生物種は、何億年もの進化の過程を経て、環境に適応しながら形作られてきました。絶滅の危機に瀕する種の中には、進化の過程で獲得した特異な形質や能力を持つものも少なくありません。
例えば、オーストラリアに生息するカモノハシは、哺乳類でありながら卵を産むという特殊な生態を持っています。カモノハシの研究は、哺乳類の進化を理解する上で重要な手がかりを与えてくれます。また、ニュージーランドのキウイは、鳥類でありながら、高度に発達した嗅覚を持ち、夜行性の生活を送っています。キウイの生態は、鳥類の適応放散の過程を物語る貴重な例と言えるでしょう。
このように、絶滅危惧種の多くは、生物進化の歴史を体現する存在なのです。彼らを保護することは、何億年もの時を超えて受け継がれてきた生命の物語を未来につなぐことに他なりません。進化の過程で獲得された特異な形質や能力は、将来の環境変化への適応を助ける貴重な遺伝的資源となる可能性も秘めているのです。
種の保全は、進化の可能性を守る営みでもあります。絶滅してしまった種が持っていた遺伝情報は、二度と取り戻すことができません。今、絶滅の危機に直面している種を守ることは、生命の進化の歴史に敬意を払い、その可能性を未来につなぐ私たちの責務なのかもしれません。
生物の探求と種の保全
生物の世界には、まだ私たちの知らない驚くべき存在が数多く潜んでいます。新種の発見は後を絶たず、2021年にはベトナムで大型の植物食哺乳類「サオラ」の新たな個体が確認されるなど、絶滅危惧種に関する新知見も相次いでいます。
絶滅危惧種の保護は、未知なる生物の存在を探求し、その生態を明らかにする営みでもあります。絶滅の危機に瀕する種の中には、人知れず進化の道を歩んできた「クリプティック種(隠蔽種)」も存在します。彼らの存在は、私たちの想像をはるかに超えた生物の多様性を示唆しているのです。
例えば、東南アジアのメコン川流域では、過去20年間で2000種以上の新種が発見されています。その中には、絶滅が危惧される「メコンオオナマズ」など、特異な生態を持つ種も含まれています。また、マダガスカルでは、「ミツユビナマケモノ」と呼ばれる原猿類の新種が次々と見つかっています。彼らの多くは、限られた地域にのみ生息する絶滅危惧種でもあります。
絶滅危惧種を守ることは、生物の世界の神秘を探求する機会を守ることでもあるのです。未知の種との出会いは、私たちに生命の豊かさと可能性を教えてくれます。そして、その感動は、種の保全への思いを新たにする原動力ともなるでしょう。
生物の探求と種の保全は、表裏一体の営みなのです。絶滅の危機に瀕する種を守りながら、生命の神秘に飽くなき探究心を注ぐこと。そこには、私たち人類の知的好奇心を満たす喜びもあるはずです。
種の保全と生物模倣(バイオミミクリー)
絶滅危惧種は、長い進化の過程で獲得した特異な能力を持っていることがあります。これらの能力は、持続可能な社会の実現に向けた技術革新のヒントとなる可能性を秘めています。生物模倣(バイオミミクリー)と呼ばれるアプローチは、絶滅危惧種を含む生物の優れた能力を工学的に応用する試みです。
例えば、サメ肌の特殊な表面構造は、水の抵抗を減らし、高速で泳ぐことを可能にしています。この構造を模倣した船底塗料は、船舶の燃費改善に役立てられています。また、ヤモリの足の裏にある極細の毛は、強力な接着力を生み出します。このメカニズムを応用した接着剤の開発が進められているのです。
また、シロアリの巣の構造は、高い断熱性と換気性を実現しています。この原理を建築デザインに取り入れることで、省エネルギーと快適性を両立する建物の設計が可能になります。アリの行動原理を応用した最適化アルゴリズムは、物流の効率化などに役立てられています。
このように、絶滅危惧種が持つ特異な能力は、私たち人類が直面する課題を解決するための手がかりとなり得るのです。種の保全は、バイオミミクリーの可能性を広げる源泉でもあります。絶滅危惧種を守り、その生態を探求することは、イノベーションの種を未来に残すことにもつながっているのです。
生物文化多様性(バイオカルチュラル・ダイバーシティ)と種の保全
生物多様性は、文化の多様性とも密接に関わっています。世界各地の先住民族をはじめとする地域社会は、長年にわたって自然と共生し、固有の文化を育んできました。このような生物と文化の多様性の関係性は、「生物文化多様性(バイオカルチュラル・ダイバーシティ)」と呼ばれています。
絶滅危惧種の中には、特定の地域の文化と深く結びついている種も少なくありません。例えば、アマゾンに生息するアマゾンマナティーは、先住民族の神話や芸術のモチーフとして登場します。また、太平洋の島々に生息するオオウミガメは、多くの島嶼民族にとって神聖な存在であり、儀礼や伝統的な資源管理の対象となってきました。
これらの種が絶滅の危機に瀕しているということは、それぞれの地域の文化的アイデンティティが失われる危険性をはらんでいるのです。種の保全は、生物多様性だけでなく、文化の多様性を守る営みでもあります。
また、伝統的な生態学的知識(TEK)は、絶滅危惧種の保全に重要な役割を果たすことができます。地域社会が長年にわたって培ってきた自然との付き合い方の知恵は、科学的な保全手法を補完し、より効果的な保全を可能にするのです。
絶滅危惧種を守ることは、地域の文化や伝統的知識を尊重し、次世代に引き継ぐことでもあります。生物と文化の多様性を一体のものとしてとらえ、その保全に取り組むことが求められているのです。
種の保全と自然の権利
近年、自然を権利の主体として認める「自然の権利」の考え方が、国際的にも広がりを見せています。このアプローチは、自然を人間社会から独立した存在として位置づけ、その固有の価値を尊重しようとするものです。
例えば、ニュージーランドでは、2014年にワンガヌイ川が法的権利を持つ存在として認められました。また、エクアドルやボリビアでは、憲法に自然の権利が明記されています。これらの動きは、自然保護の新たなパラダイムとして注目を集めているのです。
自然の権利の考え方は、絶滅危惧種の保護にも重要な意味を持ちます。種の存続は、生態系の権利の一部として位置づけることができるからです。絶滅の危機に瀕する種を守ることは、自然の権利を守ることに他ならないのです。
自然の権利は、人間中心的な自然観を問い直し、自然と人間の関係性を根本から見直す契機を与えてくれます。私たちは自然の一部であり、他の生物種と共に生きる存在なのだということ。その認識は、種の保全への思いを新たにする原動力となるはずです。
自然の尊厳を認め、その声に耳を傾けること。絶滅危惧種の存在は、私たちにそのことを問いかけているのかもしれません。
・ミレニアム生態系評価(MA)は、2001年から2005年にかけて行われた、地球規模の生態系に関する総合的な評価プロジェクトです。95カ国から1360人以上の専門家が参加し、生態系サービスと人間の福利の関係性などが評価されました。
・SATOYAMA(里山)イニシアティブは、自然と共生してきた日本の伝統的な里山のランドスケープを、現代的な課題解決のモデルとして国際的に推進するプロジェクトです。2010年の生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で提唱され、以降、国連大学を中心に活動が続けられています。
・IPBES(生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)は、生物多様性に関する科学と政策のインターフェースを担う政府間組織です。2012年に設立され、科学的な評価や能力構築などを通じて、生物多様性の保全と持続可能な利用に貢献しています。
絶滅危惧種の保護は、自然と人間の関係性を問い直し、新たな共生の在り方を模索する営みでもあります。生物の進化の歴史を未来につなぎ、文化の多様性を育み、イノベーションの種をまき、自然の尊厳に思いを致す。種の保全には、実に多様な意義があるのです。
そして、そのすべては、私たち一人一人の意識と行動に託されています。絶滅の危機に瀕する種の声に耳を澄まし、その存在の意味を問い直すこと。そこから生まれる共感と連帯の輪が、新たな希望をつむぐはずです。
かけがえのない生命の灯を守るため、私たちに何ができるのか。今こそ、その問いに向き合うとき。すべての生命の尊厳を心に刻み、共に生きる道を歩んでいくこと。それが、この地球に生きる私たちの使命です
絶滅危惧種を守る意義 生命の多様性と私たちの未来
種の保全と宇宙探査
地球上の生命の起源や進化の謎を解く上で、絶滅危惧種が持つ情報は極めて重要な意味を持ちます。生命の設計図とも言えるDNAの配列を読み解くことで、生物の進化の道筋や、環境への適応のメカニズムが明らかになりつつあります。絶滅危惧種のゲノム解析は、生命の神秘に迫る貴重な手がかりを与えてくれるのです。
さらに、地球外生命体の探査においても、絶滅危惧種の研究が重要な示唆を与えてくれます。地球上のあらゆる環境に適応して生きる生物の存在は、生命の可塑性と可能性を物語っています。絶滅危惧種の中には、極限環境に適応した特異な能力を持つ種も少なくありません。彼らの生態を研究することは、地球外の過酷な環境で生命が存在する可能性を探る上でも意義深いのです。
例えば、南米の乾燥地帯に生息するアタカマサンショウウオは、1年の大半を完全に乾燥した状態で過ごすことができます。この驚異的な耐性は、火星のような乾燥した環境で生命が存在する可能性を示唆しています。また、深海底の熱水噴出孔周辺に生息する生物は、高温・高圧・強酸性という過酷な条件に適応しています。この極限環境の生態系は、木星の衛星エウロパの氷殻下に存在すると考えられている海洋における生命の可能性を探る上でのモデルともなり得るのです。
絶滅危惧種を守ることは、地球生命の進化の歴史を未来に引き継ぐとともに、宇宙における生命の可能性を探求する私たちの夢を育むことでもあるのかもしれません。
種の保全と芸術
絶滅危惧種は、私たち人類の芸術的な感性を刺激し、創造性の源泉となってきました。彼らの美しさや力強さ、あるいは奇妙さは、芸術家たちに強いインスピレーションを与えてきたのです。
フランスの画家アンリ・ルソー
例えば、フランスの画家アンリ・ルソーは、熱帯雨林の生き生きとした情景を描いた作品で知られています。彼が描く、生命力に満ちた植物や動物たちの姿は、当時まだ謎に包まれていた熱帯の自然への憧れと畏敬の念を表現しています。また、現代美術家のマーク・ダイオンは、博物学的な手法を用いて絶滅危惧種をテーマにしたインスタレーションを制作。種の保全の重要性を訴えかける独自の表現で注目を集めています。
ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」に登場するドードーは、すでに絶滅してしまった鳥の象徴
文学の世界でも、絶滅危惧種は重要なモチーフとなっています。ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」に登場するドードーは、すでに絶滅してしまった鳥の象徴として描かれています。ダグラス・アダムスの「銀河ヒッチハイク・ガイド」では、絶滅寸前の種を救うためのプロジェクトが物語の鍵を握ります。これらの作品は、私たちに種の存続の儚さと尊さを問いかけているのです。
絶滅危惧種を守ることは、芸術の多様性を守ることでもあります。自然が失われれば、私たちはかけがえのないインスピレーションの源泉を失ってしまうかもしれません。種の保全は、私たちの創造性を育む自然の豊かさを未来につなぐ営みなのです。
種の保全と食文化 ウナギ キヌア スーパーフード
世界の食文化は、地域の自然環境と密接に関係しながら育まれてきました。絶滅危惧種の中には、伝統的な食材として利用されてきた種も少なくありません。それぞれの地域の食文化は、生物多様性の恵みの上に成り立ってきたと言っても過言ではないのです。
例えば、日本の食文化を支えてきた食材の一つに、ウナギがあります。川と海を行き来する独特のライフサイクルを持つウナギは、世界的に見ても絶滅リスクの高い種の一つです。ウナギの保全なくして、日本の食文化の継承はあり得ないのかもしれません。
また、ペルーやボリビアの高地で栽培されてきたキヌアは、その高い栄養価から「スーパーフード」として世界的に注目を集めています。気候変動に適応する能力の高さから、将来の食料安全保障の観点からも重要視されているのです。在来種を守ることは、地域の食文化を守るとともに、私たちの食の未来を守ることにもつながっています。
絶滅危惧種を守ることは、世界の多様な食文化を守ることでもあります。種の保全は、私たちの「食」を支える生物多様性の基盤を未来につないでいく営みなのです。
種の保全とエコロジカルフットプリント
私たち人類の経済活動は、地球の生態系に大きな負荷を与えています。「エコロジカルフットプリント」と呼ばれる指標は、私たちの消費生活が地球の生物生産力にどれだけの影響を及ぼしているかを示すものです。現在、人類のエコロジカルフットプリントは、地球の生物生産力の1.6倍に達していると見積もられています。つまり、私たちは地球の資源を持続不可能なペースで消費しているのです。
このような状況が絶滅危惧種に与える影響は計り知れません。生息地の減少や環境汚染、気候変動など、私たちの活動が引き起こす環境の変化が、多くの種の存続を脅かしているのです。
種の保全は、私たちのライフスタイルを見直し、エコロジカルフットプリントを削減する契機となります。絶滅の危機に瀕する種の存在は、地球の生態系が限界に近づいていることを示す警告でもあるのです。一人一人が自らの消費行動を振り返り、より持続可能な生き方を選択すること。種の保全は、そのための重要な一歩となるでしょう。
種の保全と子どもの成長
絶滅危惧種について学び、その保全活動に参加することは、子どもたちの成長にとっても大きな意味を持ちます。自然の中で生きる多様な生命に触れることは、子どもたちの感受性を豊かに育む機会となるからです。
絶滅危惧種を題材とした環境教育は、命の尊さや自然の大切さを伝える上で大きな効果を発揮します。実際に野生生物を観察し、その生態について学ぶ経験は、子どもたちの好奇心を刺激し、学ぶ意欲を高めてくれるでしょう。
また、種の保全活動へのボランティア参加は、子どもたちの社会性や協調性を育む機会にもなります。仲間と協力しながら、具体的な課題解決に取り組む経験は、子どもたちの成長にとって非常に重要です。
絶滅危惧種について学び、その保全に取り組むことは、次世代を担う子どもたちに自然の大切さを伝え、その感性を育むことにつながります。種の保全は、未来への希望をつなぐ教育の営みでもあるのです。
以上のように、絶滅危惧種の保護には実に多様な意義があります。種の保全は、生物多様性という地球の財産を未来に引き継ぐとともに、私たち自身の暮らしや文化、芸術、食、教育など、あらゆる側面に深く関わっているのです。
そして、その意義を実現するためには、社会の幅広い参画が欠かせません。研究者や政策立案者、NGOだけでなく、企業や市民、そして子どもたち一人一人が、種の保全に自分なりの形で関わっていくこと。そうした多様な主体の協働が、絶滅の危機に瀕する種を救う大きな力となるはずです。
絶滅危惧種の存在は、私たち人類に問いかけています。私たちはいかにして自然と共生していくのか。そして、この地球をどのような形で未来に引き継いでいくのか。その問いに向き合うことは、持続可能な社会を築いていく上で避けて通れない私たちの責務なのです。
かけがえのない生命を守るために、私たちに何ができるのか。その問いに、一人一人が自分なりの答えを探していくこと。そこから生まれる智慧と行動の輪が、きっと新たな未来への道を拓いていくはずです。すべての生命の尊厳を胸に、種の保全という希望の営みを、共に進めていきましょう。
絶滅危惧種を守るためにできること 生物多様性を未来につなぐ知恵と行動
生息地の保護と再生 保護区の設定
絶滅危惧種の多くは、開発や環境破壊によって生息地を奪われ、存続の危機に瀕しています。彼らを守るためには、残された生息地を確実に保護するとともに、失われた生息地を再生していく取り組みが欠かせません。
まずは、絶滅危惧種の生息域を包括的に保護する保護区の設定が重要です。例えば、中国四川省のジャイアントパンダ保護区ネットワークは、パンダの主要な生息地を効果的にカバーしています。保護区内では、森林伐採や狩猟が厳しく制限され、パンダの生息環境が維持されているのです。
また、分断化された生息地をつなぐ「コリドー(回廊)」の整備も重要な戦略です。コスタリカの「パソ・デ・ラ・ダンタ(ダンタの歩み)」プロジェクトでは、森林の断片化によって孤立したバイオリザーブを、コリドーでつなぐ取り組みが進められています。これにより、ジャガーなどの大型哺乳類の移動が可能になり、個体群の存続力が高まることが期待されています。
熱帯雨林の再生プロジェクト
さらに、劣化した生息地の再生も重要な課題です。インドネシアのボルネオ島では、違法伐採や火災によって失われた熱帯雨林の再生プロジェクトが進行中です。荒廃した土地にフタバガキ科の樹木を中心に植林することで、オランウータンなどの絶滅危惧種の生息地が少しずつ回復してきています。
生息地の保護と再生は、地域社会の理解と協力なくしては成し得ません。地域の人々の生活と自然保護の両立を図る「保全と開発のプロジェクト(ICDPs: Integrated Conservation and Development Projects)」の取り組みが世界各地で進められています。例えば、ウガンダのブウィンディ国立公園では、ゴリラ観光から得られる収益を地域社会の発展に還元することで、住民の保護区管理への参画を促しているのです。
絶滅危惧種の生息地を守り、再生していくためには、科学的知見に基づく戦略的なアプローチと、地域に根ざした参加型の取り組みの両輪が欠かせません。国際社会と地域社会が協働し、長期的視野に立って生息地の保全に取り組むこと。それが、絶滅の危機に瀕する種を救う大きな原動力となるはずです。
密漁・密猟・違法取引対策の強化
絶滅危惧種の多くは、密猟や違法取引の犠牲となっています。象牙を求めるゾウの密猟、高級食材として取引されるハナシャクヤクの盗掘、ペット目的で捕獲されるヨウムの違法取引など、その例は枚挙に暇がありません。密猟・違法取引の撲滅は、種の保全における喫緊の課題と言えるでしょう。
「CITES(ワシントン条約)」をはじめとする国際的な取り締まりの強化が求められます。例えば、象牙取引に関しては、国際的な全面禁止を求める声が高まっています。2016年のCITES総会では、国内市場の閉鎖を各国に勧告する決議が採択されました。日本を含む多くの国で象牙の国内取引規制が進められています。
また、密猟・違法取引を水際で防ぐためには、取締機関の能力強化が欠かせません。ケニアやタンザニアでは、密猟対策部隊の強化と装備の充実が図られ、ゾウの密猟が大幅に減少しています。最新のドローン技術を活用した監視体制の構築も進められているのです。
違法取引の需要を減らすための消費者教育も重要です。中国やベトナムでは、かつてゾウやサイの角が高級薬材として珍重されてきましたが、政府主導のキャンペーンによって消費者の意識が変化しつつあります。伝統医学と西洋医学の融合を図る中国の「TCM(伝統中医薬)モダナイゼーション」戦略は、絶滅危惧種由来の薬材からの代替を促す上で注目すべき動きと言えるでしょう。
密猟・違法取引対策は、国際社会が一丸となって取り組むべき課題です。野生生物の違法取引は、組織犯罪やテロ資金とも関連する複合的な問題だからです。CITESを軸とした国際協調と、現場の取り締まり強化、消費者の意識改革を三位一体で進めていくこと。それが、絶滅の危機に瀕する種を密猟・違法取引の脅威から守る鍵となるはずです。
生息域外保全の推進 野生下での存続が極めて難しい場合
絶滅危惧種の中には、野生下での存続が極めて難しい状況に追い込まれている種もあります。そうした種を救うためには、動物園や植物園などでの生息域外保全の取り組みが欠かせません。
生息域外保全には、種の絶滅を防ぐ「保険」としての意味合いがあります。野生個体群が壊滅的な打撃を受けた場合でも、飼育下の個体から種を復元できる可能性を残すのです。絶滅危惧種の飼育繁殖と野生復帰は、多くの動物園の重要な使命となっています。
コウノトリは、1971年に日本で野生絶滅→工繁殖
例えば、コウノトリは、1971年に日本で野生絶滅しましたが、人工繁殖された個体の放鳥によって、野生個体群の再建が進められています。2005年以降、毎年のように野生下でのヒナの誕生が確認されており、着実に野生復帰の成果が上がっているのです。
ハワイ植物保全センター
また、ハワイの固有植物の多くは、外来種の影響で絶滅の危機に瀕しています。ハワイ植物保全センターでは、絶滅寸前の種の栽培と種子保存に取り組んでいます。栽培下で個体数を回復させた後、本来の生育地に再導入する試みも行われているのです。
生息域外保全の取り組みは、野生復帰を最終目標としつつも、その過程で得られる知見は種の保全戦略を立てる上で貴重な意味を持ちます。飼育下での繁殖生理の解明は、野生個体群の保護増殖にも役立ちます。また、動物園での展示や教育プログラムは、絶滅危惧種の存在を広く伝え、保全の重要性を社会に訴える上でも大きな役割を果たしているのです。
野生生物の生息地内保全が種の存続の根幹をなすことは言うまでもありません。しかし、それだけでは守れない種もいる現実を私たちは直視する必要があります。生息域外保全は、絶滅の淵に立つ種に最後の希望を与える試みなのです。そこで培われた知見と技術を、野生個体群の保全に還元していくこと。生息域内保全と生息域外保全の両輪が力を合わせてこそ、絶滅危惧種の未来を拓くことができるでしょう。
保全生物学の発展
種の保全の取り組みを科学的な基盤の上に置くためには、保全生物学の発展が欠かせません。保全生物学とは、生物多様性の保全に関わる科学的な研究と実践を包括する学際的な分野です。絶滅危惧種の現状把握から、保全計画の立案、効果検証に至るまで、保全生物学の知見は種の存続を左右する鍵を握っているのです。
まずは、絶滅危惧種の個体数や分布、生態などの基礎情報の収集が何より重要です。「レッドリスト」と呼ばれる絶滅リスクのランク付けは、現状評価と保全の優先順位付けに役立ちます。近年は、リモートセンシング技術やGIS(地理情報システム)、eDNAなどの新しい手法も導入され、より効率的かつ精緻なモニタリングが可能になっています。
また、絶滅リスクの要因を解明し、有効な保全策を立案するためには、生息地の喪失や分断化、密猟・違法取引、外来種の影響など、様々な脅威について総合的に分析する必要があります。保全生物学は、分子生物学や生態学、社会科学など多様な分野の知見を動員しながら、保全上の課題解決に取り組んでいるのです。
さらに、保全の取り組みの成果を評価し、順応的に管理していくことも保全生物学の重要な役割です。例えば、生息地の保護や再生の効果を検証するためには、長期的なモニタリングと統計解析が欠かせません。ICDPsの取り組みが地域社会に与える影響を評価するためには、社会科学的なアプローチも必要とされます。
保全生物学の発展は、専門家の育成と、研究基盤の強化なくしては成し得ません。世界各地の大学で保全生物学の教育プログラムが開設され、次世代の保全生物学者が育っています。また、IUCN(国際自然保護連合)やWWF(世界自然保護基金)などの国際NGOは、保全生物学の研究を支援し、その成果を政策提言や現場の保全活動に活かす上で重要な役割を果たしているのです。
科学的な知見に基づいて種の保全に取り組むこと。そのための羅針盤となるのが保全生物学です。絶滅の危機に瀕する種を守るためには、保全生物学の一層の発展と、その知見の社会実装が求められています。研究者と実践者、政策立案者と市民が協働しながら、保全生物学の英知を結集していくこと。それが、種の存続という共通の目標に向かって私たちを導いてくれるはずです。
保全政策とガバナンス ワシントン条約や、ラムサール条約、ボン条約
絶滅危惧種を守るためには、科学的な知見に基づく保全政策の立案と、それを実行に移すためのガバナンス体制の構築が欠かせません。国内法の整備から国際条約の履行、予算の確保から執行体制の強化まで、政策とガバナンスのあり方が種の命運を左右すると言っても過言ではありません。
まずは、国内の法制度の整備が保全の基盤となります。日本の種の保存法のように、絶滅のおそれのある種を指定し、その保護増殖事業を進める法的枠組みを持つことが重要です。開発行為が絶滅危惧種に与える影響を事前に評価し、回避・緩和措置を講じるための環境アセスメント制度も不可欠と言えるでしょう。
一方、渡り鳥や海洋生物など、国境を越えて移動する種の保全には、国際的な政策協調が欠かせません。ワシントン条約や、ラムサール条約、ボン条約など、野生生物の保全に関わる国際条約の履行を通じて、各国が協調して保全に取り組む体制づくりが求められています。二国間・多国間の保護区ネットワークの構築なども、国際的な種の保全を進める上で有効な手段と言えます。
また、保全政策の実効性を担保するためには、ガバナンス体制の強化が重要な課題となります。中央政府と地方政府の役割分担、省庁間の連携、NGOや地域社会など多様なステークホルダーとの協働のあり方など、ガバナンスのデザインが保全の成否を分けると言っても過言ではありません。
例えば、フィリピンのパラワン川流域では、国と地方政府、先住民族、NGOなどが協力し、「統合的流域管理」の枠組みで生物多様性の保全に取り組んでいます。流域全体の土地利用を調整し、持続可能な資源管理を図ることで、絶滅危惧種の生息環境の保全と地域の生計向上を両立させているのです。
さらに、保全政策には、確実な財源の裏付けが不可欠です。コスタリカでは、森林保全を進める土地所有者に経済的インセンティブを与える「環境サービス支払い制度」が導入されています。ドイツでは、エコロジカル・タックスの一部が自然保護の財源に充てられているのです。
絶滅危惧種を守るための戦略 生物多様性保全の鍵を握る社会の英知
種の保全は、一国の問題にとどまりません。地球規模の生物多様性の危機に対処するためには、国際社会が協調して政策とガバナンスの舵取りを行うことが何より重要です。COP(生物多様性条約締約国会議)やCITES締約国会議などの国際的な場で、絶滅危惧種の保全を主流化し、各国の取り組みを後押しする枠組みづくりが求められているのです。
保全政策の立案とガバナンス体制の構築は、科学と社会の連携なくしては成し得ません。保全生物学の知見を政策に反映させるためのインターフェースの強化と、ステークホルダー間の対話・協働を促すプラットフォームの形成。そうした科学と社会の架け橋となる仕組みづくりが、種の保全を確かなものにする鍵となるでしょう。
持続可能な資源利用の促進 ビクーニャ ワイルドシルク
絶滅危惧種の中には、地域社会にとって重要な資源となっているものも少なくありません。そうした種を守るためには、保護一辺倒ではなく、持続可能な形での資源利用を促進することが重要になります。適切な管理の下で利用と保全を両立させることで、地域社会の生計向上と種の存続という「win-win(双方にメリットのある関係)」の関係を築くことができるのです。
例えば、ペルーではアンデス山脈の高地で暮らすビクーニャの保全と持続的利用の取り組みが成功を収めています。ビクーニャは上質な毛を産することから乱獲の対象となり、一時は絶滅寸前までに追い込まれました。しかし、地域社会によるビクーニャの毛刈りと製品化を認める制度が導入されたことで、密猟が減少し、個体数が回復してきたのです。毛刈りされたビクーニャは野生に返されるため、持続的な資源利用が可能になっています。
また、マダガスカルでは、絶滅危惧種のチョウの繭から作られる「ワイルドシルク」の生産が、地域の生計向上と森林保全を両立する取り組みとして注目されています。繭の採取は在来種の餌植物の保護と一体的に行われるため、チョウの生息地が守られるとともに、森林破壊の抑制にもつながっているのです。
持続可能な資源利用を進める上では、科学的な情報に基づく順応的な管理が欠かせません。利用が種の存続を脅かすことのないよう、個体数の動向をモニタリングしながら、利用のルールを柔軟に見直していく必要があります。また、持続的な利用を通じて得られる利益を、保全活動の資金源に充てる仕組みづくりも重要な課題と言えるでしょう。
絶滅危惧種の保全と地域社会の生計向上を両立するためには、保護と利用のバランスを取ることが何より大切です。そのバランスを見出すためには、地域の人々の知恵と経験に耳を傾け、科学の知見と融合させていく協働のプロセスが欠かせません。種の存続と地域の暮らしを支える持続可能な資源利用のあり方。それを模索する取り組みは、生物多様性保全と持続可能な発展の両立を目指す私たちに、大きな示唆を与えてくれるはずです。
環境教育・自然体験活動の充実
絶滅危惧種を守るためには、社会全体で保全の重要性を共有し、行動に移していくことが欠かせません。そのためには、子どもの頃から自然との触れ合いを通じて、生物多様性の価値を実感する機会を増やしていくことが大切です。環境教育や自然体験活動の充実は、種の保全を担う次世代を育む上で特に重要な意味を持っています。
学校教育の中に、絶滅危惧種をテーマとした学習プログラムを取り入れることは、子どもたちの関心を高める有効な手段の一つです。例えば、トキの野生復帰に取り組む新潟県佐渡市では、小中学校でトキをテーマとした授業が行われています。児童・生徒が実際にトキの生息地を訪れ、保護活動の現場を体験することで、種の保全への理解と共感を深めているのです。
また、動物園や植物園、博物館などの社会教育施設も、絶滅危惧種について学ぶ重要な場となります。単なる展示にとどまらず、保全の取り組みを伝えるガイドツアーや、飼育員・研究者との対話プログラムなど、参加型の教育プログラムを充実させることが求められます。直接的な体験を通じて得られる学びは、子どもたちの心に深く刻まれるはずです。
さらに、国立公園をはじめとする自然地域は、絶滅危惧種の生息地に触れ、その保全の意義を実感する格好の場となります。エコツーリズムやネイチャーガイドといった自然体験プログラムを通じて、野生生物と私たちの暮らしのつながりを学ぶ機会を提供することが大切です。そうした自然体験は、都市部の子どもたちにこそ必要とされていると言えるでしょう。
環境教育・自然体験活動の充実は、学校、社会教育施設、NPO、地域社会など、多様な主体の連携の中で図られるべき課題です。それぞれの特性を活かした多彩なプログラムを用意し、子どもたちが主体的に参加できる機会を増やしていくこと。そうした地域ぐるみの取り組みが、種の保全を支える次世代の育成に大きく貢献するはずです。
絶滅危惧種の保全は、私たち一人一人の意識と行動の変革から始まります。自然の大切さを実感し、その恵みに感謝する心を育むこと。そして、種の存続を脅かす私たちの暮らしを見直し、できることから行動に移していくこと。環境教育・自然体験活動は、そのための種を蒔く営みです。
企業の参画と生物多様性配慮 CSR(企業の社会的責任)やESG投資

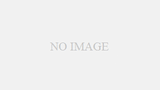
コメント